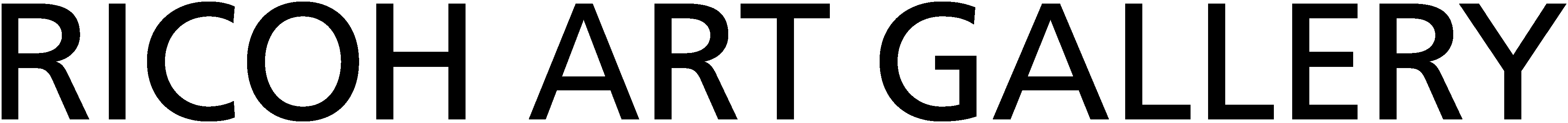REPORT

モニタに映る人間の皮膚をまとったゴリラが、リアル空間の舞踏家に同期して動くパフォーマンス映像作品《舞姫》。CG上に再現した自身の顔に多様な画像が次々と降ってきて皮膚のように張り付いていく映像作品《カオ1》――。山内祥太氏は、人間とテクノロジーの関係を考察し、リアルとバーチャルの領域を交差させるような作品を生み出す美術家だ。大学では彫刻を、大学院では映像の表現方法をひと通り学んだ。「僕は物心がついた頃からゲームやアニメが日常に溶け込んでいた世代。見ていた景色や友人との話を思い出しても、バーチャルなことが決して“非リアル”な存在ではなかった。だから、美大に入った際、西洋彫刻や西洋絵画がどうしても自分のリアリズムと結びつかなくて。もちろん、今は受け入れられるし、むしろ憧れる部分もありますが、制作をはじめた当初は、子どもの頃から見ているゲームや、バーチャルとリアルが地続きにあるような風景にリアリティを感じたわけです」と振り返る。
先述の《舞姫》や《カオ1》は、奇妙なテクスチャー(表面の質感)を放ち、見る者の胸をざわつかせる。そういった皮膚やテクスチャーに、コロナ以降、特に執着するようになったという。「一番大きかったのは、隔離されて、人と関わる方法が画面越しになったこと。フィルターを介してコミュニケーションをとることが、当たり前になっていく日常をみて、もう少し、本来テクスチャーが持つ温度感や皮膚感覚というものをデジタルのなかでも探したいな、と」
今回の個展で見せるStareReap2.5を使った作品も、細部のテクスチャーが見どころだ。《舞姫》のゴリラをモチーフにした平面、《カオ1》の彫刻、人間が服の中に描かれ「抱きしめられているのか、囚われているのか」と問いかける立体絵画《ワルツ》。その他、映像作品も会場に並ぶ。使用したStareReap2.5の技術について「テクスチャーを表現することに親和性が高く、画面の奥にあるイメージを実体化させることができる技術」と山内氏。そして「今回も、ゴリラがまとう人間の皮膚感やドレスの生地感などをリアルに表現できたと思います」と自信をみせた。
作品の原型はCGで生成したデータだ。それがリアリティを感じさせるとはどういうことか? そう問うと山内氏は「触るように見る、目で触るようなことができたとき、そこにひとつのリアリティがあるのかもしれない」と答えた。「“リアリティ(現実感)があること”と“リアル(現実)であること”って必ずしも同じではない。実は、その違いを僕はアートをやりながら探しているところもある。リアリティとは、錯覚や違和感も含め何かを強く実感すること。だとしたら実感は現実や真実と違ってもいいわけです。実際に、虚構のものがバーチャルな空間にあっても、そこにリアリティを感じる時もありますから。そのリアリティの源を探していくことは、アーティストだけでなく、今生きている人の命題なのだとも思いますね」
その点で、《ワルツ》や《カオ1》など、展示作品にトロンプルイユ的な絵画の要素もつ作品があるのも興味深い。長き絵画の歴史を振り返れば、画家が、目の前の風景を写実的に再現するだけでなく、たとえば、水の上に船が浮いているように見せるようなイリュージョンを探求してきた時代があった。実際に、絵画に対して憧れもあると山内氏は言う。「特に表現主義の画家やシュルリアリストの想像力に。今のテクノロジーは、さまざまなデバイスを使いながら、画面の中にあるものをいかに実体化できるかを目指していると思います。つまり、画像のなかに広がる世界を、実際に“見たかのようにさせる”のではなくそれを“見させる”、匂いがあるように“思わせる”のではなく、実際に匂いを“感じさせる”のがひとつのゴール。想像ではなく、現実に体験できることが革新だという価値観が背後にあるわけです。その一方で、絵画には想像することが残されている。それを見捨てたくないのかもしれません」
「そういう意味では、僕たちは過渡期に生きているのだなって思います」。そしてこう続けた。「VR装置がもっと薄くなり、物質感がないくらいまで身体化されたら、リアルやリアリティのかたちも変わってくるかもしれない。いまはその長い過渡期で、きっとStareReap2.5も、そういう過渡期的な技術として大きな価値があるのでは。4次元ではない、2次元と3次元の間の表現。立体でも平面でもどちらでもない。過渡期的。だからこそ、まだ過渡期にある僕たちはその表現に揺さぶられるのだと思います」
先述の《舞姫》や《カオ1》は、奇妙なテクスチャー(表面の質感)を放ち、見る者の胸をざわつかせる。そういった皮膚やテクスチャーに、コロナ以降、特に執着するようになったという。「一番大きかったのは、隔離されて、人と関わる方法が画面越しになったこと。フィルターを介してコミュニケーションをとることが、当たり前になっていく日常をみて、もう少し、本来テクスチャーが持つ温度感や皮膚感覚というものをデジタルのなかでも探したいな、と」
今回の個展で見せるStareReap2.5を使った作品も、細部のテクスチャーが見どころだ。《舞姫》のゴリラをモチーフにした平面、《カオ1》の彫刻、人間が服の中に描かれ「抱きしめられているのか、囚われているのか」と問いかける立体絵画《ワルツ》。その他、映像作品も会場に並ぶ。使用したStareReap2.5の技術について「テクスチャーを表現することに親和性が高く、画面の奥にあるイメージを実体化させることができる技術」と山内氏。そして「今回も、ゴリラがまとう人間の皮膚感やドレスの生地感などをリアルに表現できたと思います」と自信をみせた。
作品の原型はCGで生成したデータだ。それがリアリティを感じさせるとはどういうことか? そう問うと山内氏は「触るように見る、目で触るようなことができたとき、そこにひとつのリアリティがあるのかもしれない」と答えた。「“リアリティ(現実感)があること”と“リアル(現実)であること”って必ずしも同じではない。実は、その違いを僕はアートをやりながら探しているところもある。リアリティとは、錯覚や違和感も含め何かを強く実感すること。だとしたら実感は現実や真実と違ってもいいわけです。実際に、虚構のものがバーチャルな空間にあっても、そこにリアリティを感じる時もありますから。そのリアリティの源を探していくことは、アーティストだけでなく、今生きている人の命題なのだとも思いますね」
その点で、《ワルツ》や《カオ1》など、展示作品にトロンプルイユ的な絵画の要素もつ作品があるのも興味深い。長き絵画の歴史を振り返れば、画家が、目の前の風景を写実的に再現するだけでなく、たとえば、水の上に船が浮いているように見せるようなイリュージョンを探求してきた時代があった。実際に、絵画に対して憧れもあると山内氏は言う。「特に表現主義の画家やシュルリアリストの想像力に。今のテクノロジーは、さまざまなデバイスを使いながら、画面の中にあるものをいかに実体化できるかを目指していると思います。つまり、画像のなかに広がる世界を、実際に“見たかのようにさせる”のではなくそれを“見させる”、匂いがあるように“思わせる”のではなく、実際に匂いを“感じさせる”のがひとつのゴール。想像ではなく、現実に体験できることが革新だという価値観が背後にあるわけです。その一方で、絵画には想像することが残されている。それを見捨てたくないのかもしれません」
「そういう意味では、僕たちは過渡期に生きているのだなって思います」。そしてこう続けた。「VR装置がもっと薄くなり、物質感がないくらいまで身体化されたら、リアルやリアリティのかたちも変わってくるかもしれない。いまはその長い過渡期で、きっとStareReap2.5も、そういう過渡期的な技術として大きな価値があるのでは。4次元ではない、2次元と3次元の間の表現。立体でも平面でもどちらでもない。過渡期的。だからこそ、まだ過渡期にある僕たちはその表現に揺さぶられるのだと思います」
モニタに映る人間の皮膚をまとったゴリラが、リアル空間の舞踏家に同期して動くパフォーマンス映像作品《舞姫》。CG上に再現した自身の顔に多様な画像が次々と降ってきて皮膚のように張り付いていく映像作品《カオ1》――。山内祥太氏は、人間とテクノロジーの関係を考察し、リアルとバーチャルの領域を交差させるような作品を生み出す美術家だ。大学では彫刻を、大学院では映像の表現方法をひと通り学んだ。「僕は物心がついた頃からゲームやアニメが日常に溶け込んでいた世代。見ていた景色や友人との話を思い出しても、バーチャルなことが決して“非リアル”な存在ではなかった。だから、美大に入った際、西洋彫刻や西洋絵画がどうしても自分のリアリズムと結びつかなくて。もちろん、今は受け入れられるし、むしろ憧れる部分もありますが、制作をはじめた当初は、子どもの頃から見ているゲームや、バーチャルとリアルが地続きにあるような風景にリアリティを感じたわけです」と振り返る。
先述の《舞姫》や《カオ1》は、奇妙なテクスチャー(表面の質感)を放ち、見る者の胸をざわつかせる。そういった皮膚やテクスチャーに、コロナ以降、特に執着するようになったという。「一番大きかったのは、隔離されて、人と関わる方法が画面越しになったこと。フィルターを介してコミュニケーションをとることが、当たり前になっていく日常をみて、もう少し、本来テクスチャーが持つ温度感や皮膚感覚というものをデジタルのなかでも探したいな、と」
今回の個展で見せるStareReap2.5を使った作品も、細部のテクスチャーが見どころだ。《舞姫》のゴリラをモチーフにした平面、《カオ1》の彫刻、人間が服の中に描かれ「抱きしめられているのか、囚われているのか」と問いかける立体絵画《ワルツ》。その他、映像作品も会場に並ぶ。使用したStareReap2.5の技術について「テクスチャーを表現することに親和性が高く、画面の奥にあるイメージを実体化させることができる技術」と山内氏。そして「今回も、ゴリラがまとう人間の皮膚感やドレスの生地感などをリアルに表現できたと思います」と自信をみせた。
作品の原型はCGで生成したデータだ。それがリアリティを感じさせるとはどういうことか? そう問うと山内氏は「触るように見る、目で触るようなことができたとき、そこにひとつのリアリティがあるのかもしれない」と答えた。「“リアリティ(現実感)があること”と“リアル(現実)であること”って必ずしも同じではない。実は、その違いを僕はアートをやりながら探しているところもある。リアリティとは、錯覚や違和感も含め何かを強く実感すること。だとしたら実感は現実や真実と違ってもいいわけです。実際に、虚構のものがバーチャルな空間にあっても、そこにリアリティを感じる時もありますから。そのリアリティの源を探していくことは、アーティストだけでなく、今生きている人の命題なのだとも思いますね」
その点で、《ワルツ》や《カオ1》など、展示作品にトロンプルイユ的な絵画の要素もつ作品があるのも興味深い。長き絵画の歴史を振り返れば、画家が、目の前の風景を写実的に再現するだけでなく、たとえば、水の上に船が浮いているように見せるようなイリュージョンを探求してきた時代があった。実際に、絵画に対して憧れもあると山内氏は言う。「特に表現主義の画家やシュルリアリストの想像力に。今のテクノロジーは、さまざまなデバイスを使いながら、画面の中にあるものをいかに実体化できるかを目指していると思います。つまり、画像のなかに広がる世界を、実際に“見たかのようにさせる”のではなくそれを“見させる”、匂いがあるように“思わせる”のではなく、実際に匂いを“感じさせる”のがひとつのゴール。想像ではなく、現実に体験できることが革新だという価値観が背後にあるわけです。その一方で、絵画には想像することが残されている。それを見捨てたくないのかもしれません」
「そういう意味では、僕たちは過渡期に生きているのだなって思います」。そしてこう続けた。「VR装置がもっと薄くなり、物質感がないくらいまで身体化されたら、リアルやリアリティのかたちも変わってくるかもしれない。いまはその長い過渡期で、きっとStareReap2.5も、そういう過渡期的な技術として大きな価値があるのでは。4次元ではない、2次元と3次元の間の表現。立体でも平面でもどちらでもない。過渡期的。だからこそ、まだ過渡期にある僕たちはその表現に揺さぶられるのだと思います」
先述の《舞姫》や《カオ1》は、奇妙なテクスチャー(表面の質感)を放ち、見る者の胸をざわつかせる。そういった皮膚やテクスチャーに、コロナ以降、特に執着するようになったという。「一番大きかったのは、隔離されて、人と関わる方法が画面越しになったこと。フィルターを介してコミュニケーションをとることが、当たり前になっていく日常をみて、もう少し、本来テクスチャーが持つ温度感や皮膚感覚というものをデジタルのなかでも探したいな、と」
今回の個展で見せるStareReap2.5を使った作品も、細部のテクスチャーが見どころだ。《舞姫》のゴリラをモチーフにした平面、《カオ1》の彫刻、人間が服の中に描かれ「抱きしめられているのか、囚われているのか」と問いかける立体絵画《ワルツ》。その他、映像作品も会場に並ぶ。使用したStareReap2.5の技術について「テクスチャーを表現することに親和性が高く、画面の奥にあるイメージを実体化させることができる技術」と山内氏。そして「今回も、ゴリラがまとう人間の皮膚感やドレスの生地感などをリアルに表現できたと思います」と自信をみせた。
作品の原型はCGで生成したデータだ。それがリアリティを感じさせるとはどういうことか? そう問うと山内氏は「触るように見る、目で触るようなことができたとき、そこにひとつのリアリティがあるのかもしれない」と答えた。「“リアリティ(現実感)があること”と“リアル(現実)であること”って必ずしも同じではない。実は、その違いを僕はアートをやりながら探しているところもある。リアリティとは、錯覚や違和感も含め何かを強く実感すること。だとしたら実感は現実や真実と違ってもいいわけです。実際に、虚構のものがバーチャルな空間にあっても、そこにリアリティを感じる時もありますから。そのリアリティの源を探していくことは、アーティストだけでなく、今生きている人の命題なのだとも思いますね」
その点で、《ワルツ》や《カオ1》など、展示作品にトロンプルイユ的な絵画の要素もつ作品があるのも興味深い。長き絵画の歴史を振り返れば、画家が、目の前の風景を写実的に再現するだけでなく、たとえば、水の上に船が浮いているように見せるようなイリュージョンを探求してきた時代があった。実際に、絵画に対して憧れもあると山内氏は言う。「特に表現主義の画家やシュルリアリストの想像力に。今のテクノロジーは、さまざまなデバイスを使いながら、画面の中にあるものをいかに実体化できるかを目指していると思います。つまり、画像のなかに広がる世界を、実際に“見たかのようにさせる”のではなくそれを“見させる”、匂いがあるように“思わせる”のではなく、実際に匂いを“感じさせる”のがひとつのゴール。想像ではなく、現実に体験できることが革新だという価値観が背後にあるわけです。その一方で、絵画には想像することが残されている。それを見捨てたくないのかもしれません」
「そういう意味では、僕たちは過渡期に生きているのだなって思います」。そしてこう続けた。「VR装置がもっと薄くなり、物質感がないくらいまで身体化されたら、リアルやリアリティのかたちも変わってくるかもしれない。いまはその長い過渡期で、きっとStareReap2.5も、そういう過渡期的な技術として大きな価値があるのでは。4次元ではない、2次元と3次元の間の表現。立体でも平面でもどちらでもない。過渡期的。だからこそ、まだ過渡期にある僕たちはその表現に揺さぶられるのだと思います」

作家の山内祥太氏。タイトルの『Ballet Mécanique』は、作家フェルナン・レジェの実験映画、坂本龍一の楽曲からとった。「『バレエ(=身体)、メカニック(=機械)』の言葉の響きがずっと気になっていた」と語る。
作家の山内祥太氏。タイトルの『Ballet Mécanique』は、作家フェルナン・レジェの実験映画、坂本龍一の楽曲からとった。「『バレエ(=身体)、メカニック(=機械)』の言葉の響きがずっと気になっていた」と語る。

《カオ》の試作を“触るように見る”山内氏。StareReap2.5で印刷したものをお面などに使われるバキューム製法で顔の形に形成した彫刻作品。
《カオ》の試作を“触るように見る”山内氏。StareReap2.5で印刷したものをお面などに使われるバキューム製法で顔の形に形成した彫刻作品。

《舞姫》のゴリラをモチーフにしたStareReap2.5印刷の試作品。「少し気持ち悪く、同時にエロティシズムを感じるような皮膚感を見てもらいたい」
《舞姫》のゴリラをモチーフにしたStareReap2.5印刷の試作品。「少し気持ち悪く、同時にエロティシズムを感じるような皮膚感を見てもらいたい」
山内祥太
1992年、岐阜県生まれ。2016年、東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。主な展覧会に、『第二のテクスチュア(感触)』(Gallery TOH、2021年)、『水の波紋2021展 消えゆく風景から ― 新たなランドスケープ』(ワタリウム美術館、2021年)、『多層世界の中のもうひとつのミュージアム——ハイパーICCへようこそ』(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、2021年)、『TERRADA ART AWARD 2021 ファイナリスト展』(寺田倉庫 G3-6F、2021年)。
1992年、岐阜県生まれ。2016年、東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。主な展覧会に、『第二のテクスチュア(感触)』(Gallery TOH、2021年)、『水の波紋2021展 消えゆく風景から ― 新たなランドスケープ』(ワタリウム美術館、2021年)、『多層世界の中のもうひとつのミュージアム——ハイパーICCへようこそ』(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、2021年)、『TERRADA ART AWARD 2021 ファイナリスト展』(寺田倉庫 G3-6F、2021年)。

山内祥太
1992年、岐阜県生まれ。2016年、東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。主な展覧会に、『第二のテクスチュア(感触)』(Gallery TOH、2021年)、『水の波紋2021展 消えゆく風景から ― 新たなランドスケープ』(ワタリウム美術館、2021年)、『多層世界の中のもうひとつのミュージアム——ハイパーICCへようこそ』(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、2021年)、『TERRADA ART AWARD 2021 ファイナリスト展』(寺田倉庫 G3-6F、2021年)。
1992年、岐阜県生まれ。2016年、東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。主な展覧会に、『第二のテクスチュア(感触)』(Gallery TOH、2021年)、『水の波紋2021展 消えゆく風景から ― 新たなランドスケープ』(ワタリウム美術館、2021年)、『多層世界の中のもうひとつのミュージアム——ハイパーICCへようこそ』(NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、2021年)、『TERRADA ART AWARD 2021 ファイナリスト展』(寺田倉庫 G3-6F、2021年)。